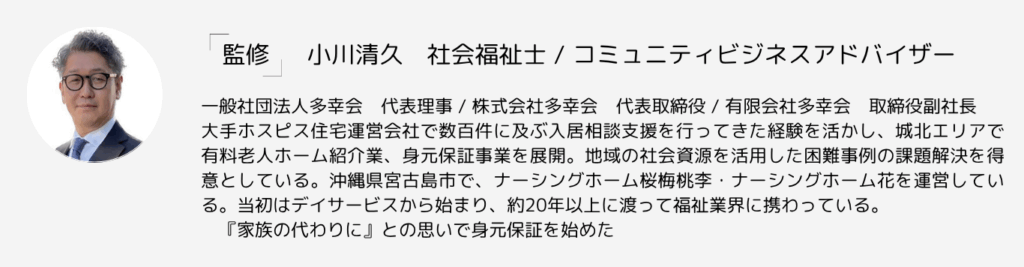任意後見人制度とは?将来に備える安心の仕組み
老後の備えとして注目されている「任意後見人制度」。元気なうちに信頼できる相手と契約しておくことで、将来的な不安を少しでも軽減できます。この記事では、制度の基本からできること・できないこと、手続きの流れや費用まで、わかりやすく解説します。
任意後見制度は「判断能力があるうちに契約する制度」
任意後見制度は、将来判断力が衰えたときに備えて、あらかじめ信頼できる人にサポートをお願いする契約です。契約は公正証書で行い、実際に判断力が低下したタイミングで、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選び、そこから制度がスタートします。
将来の認知症や病気への備えとして関心が高まる理由
- 家族に過度な負担をかけたくない
- 身近に頼れる人がいない
- 老後の暮らしを自分らしく整えておきたい
制度に関わる人たち
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| 本人 | 制度を利用する人。契約の依頼者。 |
| 任意後見人 | 将来、本人の代理として支援を行う人。 |
| 任意後見監督人 | 家庭裁判所が選任し、任意後見人の業務をチェックする第三者。 |
任意後見制度でできること・できないこと
できることの例
- 銀行口座の管理、振込などの金銭面のサポート
- 介護・医療サービスの契約手続き
- 施設とのやり取りや生活全般の支援
対応できないことに注意
- 施設入居時などの身元保証
- 医療行為への同意(手術や延命治療など)
- 死後の手続き(葬儀や相続など)
任意後見制度は万能ではないため、契約内容を事前にしっかり確認することが大切です。
任意後見制度の流れ 4つのステップ
- 後見人を選ぶ
信頼できる人を選びましょう。家族でも専門職でも構いません。 - 公正証書による契約
公証役場で正式に契約を結びます。 - 判断力の低下時に発効
契約後すぐに効力は発生しません。判断力の低下が確認された後、裁判所が監督人を選任します。 - 任意後見人の活動開始
選ばれた後見人が契約に基づいて支援を開始し、監督人が状況を見守ります。
費用と依頼先の選び方
| 項目 | 相場 |
|---|---|
| 公正証書作成費用 | 約1~2万円 |
| 専門職への報酬 | 年間 数万円~ |
| 任意後見監督人の報酬 | 月額 1~2万円程度 |
誰に依頼するか?
司法書士は財産管理に強く、弁護士は法的なトラブル対応に優れています。何よりも、「信頼できるか」が判断基準になります。
制度ではカバーできない部分と補完サービス
任意後見制度の限界
- 身元保証人が必要な場面には対応できない
- 死後の手続きには関われない
補完手段としての身元保証サービス
上記のような場面に備える方法として、民間の身元保証会社を利用するケースが増えています。入院・施設入所の保証や、死後の事務手続きなどをサポートしてくれます。
任意後見とサービスの組み合わせで安心を
任意後見制度だけではカバーしきれない範囲を、信頼できる外部サービスで補完することで、より現実的で安心感のある備えが整います。
まとめ
任意後見制度は「元気なうちに信頼できる人に将来の支援を託す制度」です。
財産管理や生活面の支援はできますが、身元保証や医療同意、死後の事務には対応していません。
制度の限界を理解したうえで、身元保証会社などとの組み合わせを検討することが安心につながります。
ご自身やご家族のこれからに向けて、「何を誰に託すか」を考える第一歩として、ぜひ任意後見制度の活用を検討してみてください。