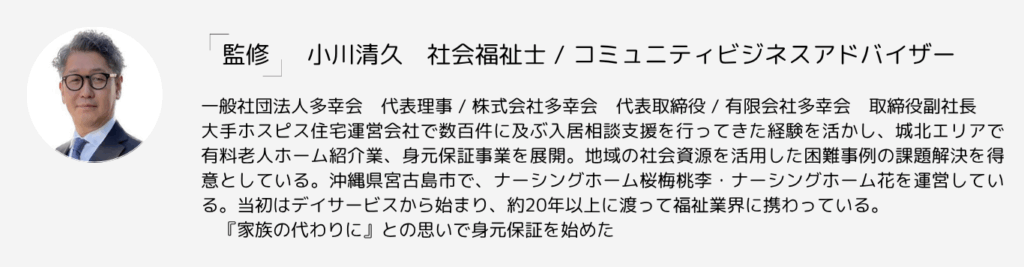「親の判断力が落ちてきた…」そんなときに知っておきたい法定後見制度とは?
高齢の親が「通帳の場所を忘れた」「よく分からない契約を結んでいた」など、判断力の低下が目立ってくると、家族としては心配がつのるものです。
財産管理、医療や介護に関する手続き、さらには親族間の意見の食い違いまで──すべてを一人で抱えるのは大きな負担です。
そんな時に選択肢として考えたいのが、「法定後見制度」です。
法定後見制度で和らぐ、よくある3つの不安
| 心配ごと | 制度によるサポート |
|---|---|
| お金の管理が難しくなってきた (詐欺・不明な出費など) | 後見人が代わりに契約内容を確認し、財産の管理を担います。 |
| 入所や医療手続きで戸惑う (本人の意思確認が困難) | 後見人が法的代理人として、必要な手続きに対応できます。 |
| 相続や介護方針を巡るトラブル | 第三者として選任された後見人が入り、冷静かつ公平な判断を促します。 |
判断力の状態に応じた3つの制度タイプ
| 制度の種類 | 該当する状態 | 支援の内容 |
|---|---|---|
| 成年後見 | ほとんど判断ができない状態(例:重度の認知症) | 後見人が全面的に生活や契約行為を代理します。 |
| 保佐 | 判断に大きな不安がある場合 | 重要な契約などに対して、同意や代理を行います。 |
| 補助 | 判断力は残っているが部分的に支援が必要な段階 | 必要な範囲に限って、補助人が関与します。 |
申立てから利用開始までの流れと必要な準備
手続きの基本ステップ
- 申立て(本人・配偶者・親族・市区町村長など)
- 家庭裁判所による審査
- 医師による診断書の提出
- 裁判所の審判、後見人の決定
費用や書類の一例
- 収入印紙:およそ800円
- 登記費用:2,600円程度
- 医師の鑑定費用:5〜10万円(地域差あり)
実際に起きやすいトラブルと事前にできる備え
- 報酬を巡る誤解:後見人の報酬について意見が分かれることがあります。
- 親族の間での意見の食い違い:誰を後見人にするかで対立が起きる場合も。
→ 専門家のアドバイスを早めにもらい、あらかじめ希望を整理しておくと安心です。
家族がいない、または頼れない場合の選択肢
利用できる代替制度の比較
| 制度名 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 市民後見人 | 自治体が選任。公的な安心感がある | 支援範囲が限られることもある |
| 法人後見 | 法人が継続的な支援を提供 | 個別対応が難しいケースもある |
| 身元保証会社の活用 | 後見制度と組み合わせてサポート (入所手続き・死後事務も対応) | 信頼性の高い会社を選ぶ必要あり |
まずは専門家への無料相談で不安を整理しよう
相談先の例
- 司法書士や行政書士などの専門職
- 地域の身元保証サービス
- 市区町村の高齢者支援窓口
制度と民間サービスを上手に組み合わせることで、家族だけで抱えずに済む体制が作れます。
自分たちに合った制度を見つけるには?
「どの制度を選ぶか」ではなく、「どんな場面で困っているのか」を基準にすることで、自分たちに合った方法が見えてきます。
家族の状況やご本人の希望に耳を傾けながら、柔軟に選んでいくことが大切です。
迷ったときは、早めの相談がカギ
判断力が完全に失われる前に動くことで、選べる選択肢も広がります。
まずは無料相談などを活用し、自分たちの状況に合った対策を見つけていきましょう。
まとめ
法定後見制度は複雑そうに見えますが、実際には家族の不安を一つずつ解消してくれる手段でもあります。
大切なのは、制度を理解し、自分たちの信頼できる支援先を見つけること。
「どこに相談すればよいか」からでも構いません。
まずは一歩踏み出して、安心できる体制づくりを始めてみませんか?