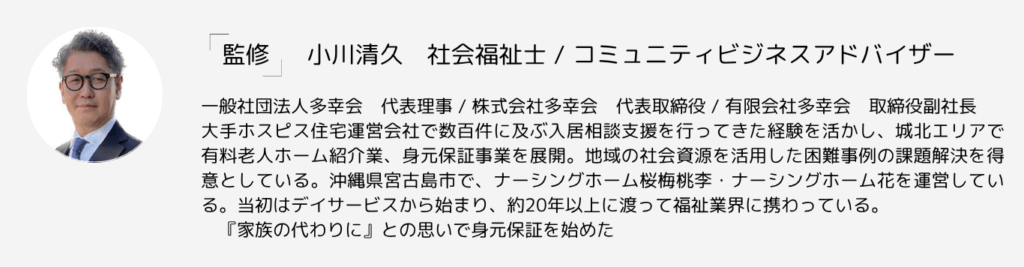遺言・遺言代用信託・遺言信託の違いを、迷わず選べるように
単語一つひとつは知っていても、聞きなじみのない言葉で何がどう違うのかわからない方も多いはず。制度の違いだけではなく、「誰が手を動かすのか」「入院・施設入居・死後事務とどう繋げるのか」までを解説します。
迷いを解く鍵は「タイミング」と「担い手」の二つ
生前に動かすか、死亡後に発動させるか
遺言は、ご本人が亡くなった時点で効力が出ます。生前は仕組みが動かないため、準備の中心は文面づくりと保管方法の選択です。これに対して遺言代用信託は、生前から運用を始められるのが大きな違いです。口座管理や定期給付、死亡後の承継までを一つの設計に落とし込み、いわば「ゆっくり走り続ける」仕組みを作れます。遺言信託は多くの場合、信託銀行が提供するサービス名で、作成・保管・執行まで伴走してくれますが、効力が反映されるのは遺言どおり死亡時です。
実務を担うのは誰か
遺言では、家族や指定された遺言執行者が相続登記や口座の解約などを進めます。遺言代用信託では、受託者(たとえば金融機関)が生前の管理から死亡後の給付・承継までを担当します。遺言信託は、信託銀行等が作成のサポートから保管、そして執行まで通しで関わる前提です。つまり、「いつ動くか」と「誰が動くか」を最初に決めておくと、その後の選択がぐっと楽になります。
違いは六つの視点で把握すると一気に見えてくる
【60秒比較表】まずは全体像
| 視点 | 遺言 | 遺言代用信託 | 遺言信託(サービス) |
|---|---|---|---|
| 主目的 | 死後の意思表示(分け方・執行者指定など) | 生前からの設計と自動承継(給付・管理・承継の“自動運転”) | 遺言の作成・保管・執行を専門機関が伴走 |
| 開始時期/効果 | 死亡時に効力 | 生前に運用開始、死亡後は次段階へ | 作成・保管は生前、効力は死亡時 |
| 検認・保管 | 自筆は検認要/法務局保管で原則検認不要/公正証書は検認不要 | 信託契約なので検認手続きは不要 | 公正証書遺言が一般的/金融機関で保管 |
| 実務カバー範囲 | 相続登記・口座解約などは家族や執行者が実行 | 受託者が信託財産の範囲で実行(給付・承継) | 執行までワンストップ支援(登記・解約等の段取り) |
| 費用の目安(幅で把握) | 作成:数万円~十数万円(公証役場手数料など別途)/執行報酬は財産規模で変動 | 設定・管理に信託報酬(残高比例・定額など)/長期で費用がかかる | 申込・保管・執行で各手数料(金融機関により体系が異なる) |
| 向いている人 | コストを抑えつつ意思を明確化したい | 認知症リスクや継続運用を重視/定期給付や承継を仕組み化したい | 実務をまとめて任せたい/家族の負担を軽くしたい |
目的の違いを言い換えると
遺言は「意思を言葉に残す」道具です。遺言代用信託は「運用と承継を仕組みに落とし込む」考え方。遺言信託は「専門家と並走して、手戻りを避ける」やり方、と覚えておくと判断が早くなります。
開始時期と効果の出方
生前から管理や給付を回したいなら、遺言代用信託が候補に上がります。死亡時に一括で反映できれば、遺言や遺言信託の枠内で十分という場面も多いものです。
方式・検認・保管の違い
自筆の遺言は方式のミスが命取りになりやすく、法務局保管や公正証書を選ぶと安心度が上がります。信託は契約がベースなので、そもそも検認という工程がありません。ここを取り違えると、手続きの順序でつまずきやすくなります。
「誰がどこまでやるのか」を先に決める
遺言は、適切な遺言執行者を決めておかないと、相続登記や口座の解約で足が止まりがちです。遺言代用信託は、信託財産に限って受託者が動ける仕組みなので、対象外の資産が残らないよう設計を詰めます。遺言信託は段取りから執行まで一気通貫で支えてくれるため、家族の負担を抑えたい家庭には向いています。
費用は「単発」か「積み上げ」か
遺言作成のコストは一度きりで、公証役場の手数料などを含めても数万円から十数万円が一般的です。信託は初期・管理・終了時のいずれか(または複合)で報酬がかかるため、期間が長くなるほど費用は積み上がります。さらに、財産規模や不動産の件数に応じて執行報酬は上下します。
どんな人に向いているか
実務を丸ごと任せたい単身の方は遺言信託と相性が良いケースが多く、再婚や連れ子がいるご家庭は公平感の調整に遺言代用信託の工夫が生きます。不動産や自社株が多い場合は、管理から売却、配分までのレールを先に敷ける点で信託設計に分があります。
迷いを三つの問いで縮める
- 資産と家族関係の棚卸し
相続人、遺留分、過去の贈与の有無など、地図を描くように状況を整理します。 - 健康状態と認知症リスク
早めに設計しておく必要があるかを見ます。 - 実務の担い手と費用の許容度
家族中心で頑張るのか、外部の伴走を頼むのかで、現実的な選択肢が変わります。
たとえば単身で、手続きは任せたいなら遺言信託へ。運用や定期給付を仕組み化したいなら遺言代用信託。費用を抑えつつ意思を明確にしたいなら公正証書遺言に遺言執行者の明記、という整理がわかりやすいでしょう。
四つの典型ケースでイメージを固める
単身・子なし世帯では、死後事務や葬送、口座解約・相続登記まで外部に委ねやすい仕組みが安心です。遺言信託と死後事務委任の組み合わせは、残された人の負担を軽くします。
再婚・連れ子ありの場合は、公平感の設計が最重要テーマ。段階承継や配分ルールをあらかじめ定められる遺言代用信託が有効です。
不動産・自社株が多いご家庭では、管理から売却、配分までの段取りを先に決めておくと詰まりにくくなります。信託を軸にすると、流れがスムーズです。
軽度の認知が疑われる、施設入居が近いといった段階なら、遺言は公正証書で確実に整えつつ、小さく遺言代用信託を回して実務の動作確認をしておくのが堅実です。
費用は五つの観点で眺めると判断しやすい
第一に遺言作成費。自筆なら最小、公正証書にすると手数料を含め数万円から十数万円ほどが目安です。第二に遺言執行報酬。財産額や不動産の件数で変わります。第三に遺言信託の手数料。申込、保管、執行の各段階で体系が分かれ、金融機関ごとに差があります。第四に遺言代用信託の報酬。初期、管理、終了時のいずれか(または併用)で、残高比例や定額など設計により異なります。最後に、戸籍・住民票、登記、評価書類、郵送といった周辺実費。表に出ない家族の手間もコストと考えると、選択の基準がクリアになります。
よくつまずく法的ポイントは、先回りで潰す
遺留分の侵害は、配分の前に試算しておくと後戻りを防げます。自筆の方式ミスや書面の紛失は、法務局保管や公正証書で回避しやすくなります。受託者の利益相反は、複数受託者や第三者の監督でバランスを取りましょう。意思能力に関しては、作成時の面談記録や診断書で将来の紛争芽を小さくできます。さらに、解約や帰属権利者の指定、死亡直後の段取り表の共有、贈与税・相続税の扱いについて専門家と歩調を合わせておくこと。いずれも、小さな準備で大きな混乱を避けられます。
身元保証・見守り・死後事務とどう繋げるか
入院や施設入居の場面では、連絡と同意の取り回し、費用立替の流れを合意書に落としておくと迷いません。死亡直後は、銀行・年金・保険・公共料金を一気に停止・整理する段取りが要になります。遺言(信託)と死後事務委任の役割分担を先に決めておくと、家族の動きがそろいます。葬送、遺品、ペットの世話といった希望は付言事項に書き、実行者(家族や専門事業者)をあらかじめ指定しておくのが現実的です。
今日から始めるなら、まず二つだけ
最初は現況のリスト化から。預貯金、証券、不動産、保険、負債を洗い出し、口座や支店、ざっくりの評価まで一列に並べます。関係者の連絡先、かかりつけ医、顧問税理士、そして身元保証の窓口も同じ紙にまとめておくと、いざという時に迷いません。
次に相談先の整理です。法的な設計や登記は弁護士・司法書士、遺言信託や代用信託の受託可否や見積もりは信託銀行へ。入院・入居・死後事務の実務ルートは身元保証会社と書面で整える。この三本立てで考えると、抜けが出にくくなります。
まとめ
選ぶ順番はシンプルです。まず「生前に動かすのか、亡くなってからでよいのか」。次に「家族で回せるのか、外部の力を借りるのか」。遺言は意思の言語化、遺言代用信託は仕組み化、遺言信託は伴走という位置づけで考えると、迷いがほどけます。入院・入居・死後事務までを視野に、法的設計と実務の動線を同じ地図に描いていきましょう。