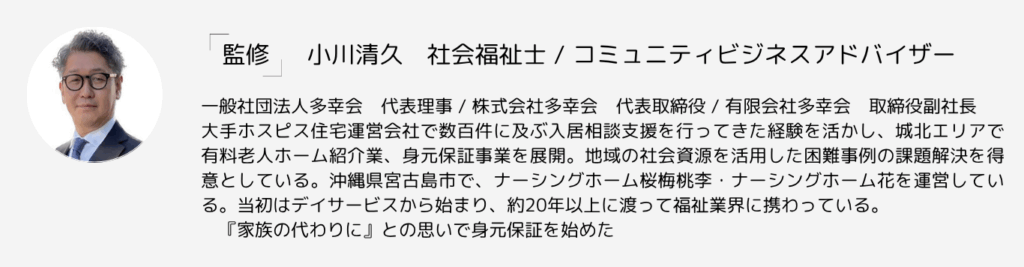信託制度の本質を知ると見えてくる3つの分類
信託とは?財産を預けるという選択
信託とは、財産の持ち主が信頼できる人にその管理や運用を託し、指定した人のために活用してもらう仕組みです。もともと欧米で生まれた制度ですが、現在では日本でも相続や資産保全の場面でよく使われるようになりました。
信託の種類は大きく3つ
信託は大きく「民事信託」「商事信託」「自己信託」に分けられます。
- 民事信託: 家族間で契約し、非営利目的で運用される(家族信託など)
- 商事信託: 信託銀行などが営利目的で実施する業務
- 自己信託: 自分で自分に財産を信託する(実務上はあまり一般的ではありません)
「家族信託」と「商事信託」はどこが違うのか
「家族信託」は民事信託に含まれ、親子や兄弟といった身内同士で財産を管理します。これに対して「商事信託」は、信託業の免許を持つ法人が、有償で他人の財産を預かる業務です。この営利・非営利という軸が大きな分かれ道です。
家族信託と商事信託の違いを比べてみよう
違いがわかりにくい家族信託と商事信託。以下の5つの観点で整理しました。
| 比較項目 | 商事信託 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 受託者 | 信託銀行や信託会社などの法人 | 親族や知人などの個人 |
| 管理対象 | 主に金融資産(不動産は制限あり) | 不動産、現金、非上場株式など幅広い |
| 目的 | 営利目的で、報酬を得ることが前提 | 老後・相続対策など家族の事情に応じて設計 |
| 費用 | 初期契約料+管理手数料が継続的にかかる | 設計・契約書作成時の費用が中心で、管理料は発生しないことが多い |
| 監督体制 | 金融庁の厳格な監督下にある | 監督機関なし(契約内容と受託者の良識に依存) |
商事信託が向いているのはこんな場合
大きな資産や金融商品を専門的に管理したい
株式や投資信託などの金融資産が多く、運用やリスク管理を専門家に任せたい場合には、商事信託が適しています。
経営者が法人資産の保全を図りたい
事業承継や法人資産の切り分けを目的とするケースでは、商事信託のスキームを活用することで、税務上・法務上のリスクを軽減できます。
家族トラブルを避けるために第三者に任せたい
親族間での対立を防ぎたい、あるいは信頼関係に不安があるといった事情がある場合には、第三者である信託会社を活用するのが安全です。
家族信託が選ばれる理由とは?
認知症リスクに備えて今のうちに手を打ちたい
親が元気なうちに契約することで、判断能力が失われた後でもスムーズに財産管理が続けられます。
信頼できる家族が受託者になれる
子どもや兄弟など、身内にしっかりした人がいる場合には、低コストで自由度の高い管理が可能です。
オーダーメイドの設計がしやすい
家族の事情に合わせて、誰にいつ何を渡すかといった細かい設計が柔軟にできる点が強みです。
判断に迷ったら、次の3点をチェック
1. 扱う資産の種類と規模
金融商品がメインなら商事信託。不動産が中心であれば、家族信託の方が向いていることが多いです。
2. 信頼できる受託者が身近にいるか
家族や親族に「任せられる人」がいれば家族信託でも安心。それが難しいなら、商事信託が安心材料になります。
3. 専門家に任せたいか、自分でコントロールしたいか
手間や責任を減らしてプロに任せたいなら商事信託。自由度を優先したいなら家族信託が選ばれます。
まとめ
家族信託と商事信託は、目的も仕組みも異なる制度です。どちらが「良い・悪い」ではなく、状況や資産内容に応じて選ぶことが大切です。いずれの制度を選ぶにしても、家族構成や財産の種類、希望する将来像などをしっかり整理しておくことが成功への近道です。